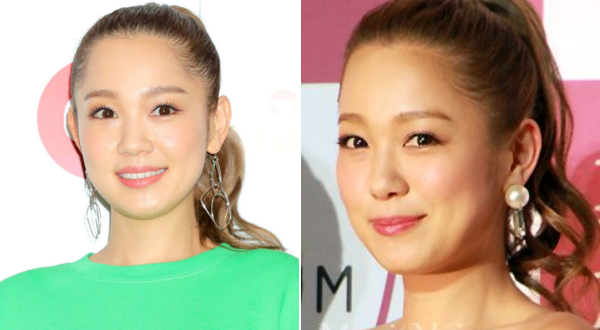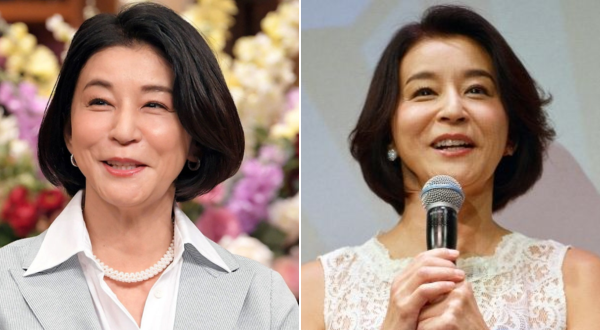来週は入学式に出席される保護者も多いのではないだろうか。また、新学期を迎え、学齢期のお子さんを持つ保護者に重くのしかかる「PTA役員の選出」は避けられない事項になりつつある。
実際、「PTAに関する意識調査」(明光義塾調べ・2025年2月調査)をみても、<非常に大きな負担を感じている>と答えた保護者が35.2%、<ある程度負担を感じている>が53.1%と、約9割の保護者がPTA役員の活動に負担を感じているという結果だった。 危機管理コンサルタントの平塚俊樹氏はこう説明する。 「毎年4月には、『PTA役員』を選ばなければならない学校がまだまだ多く存在します。自薦・他薦で決まれば御の字ですが、不毛な話し合いが延々と続くこともあります。19時に始まった話し合いが深夜まで終わらず、心配した家族が学校側にクレームを入れても『大事な会議中ですので』と取り合ってもらえないことも。 また、何時間も続く『お通夜状態』の沈黙の会議に耐えられるかどうかが運命の分かれ道とも言われています。というのも、シビレを切らして『もうこんな時間じゃないか! じゃあ、私やりますよ!』とキレる人が出るまでがワンセットだとおっしゃる保護者もいらっしゃいます。 本来、PTAは、子どもたちの健やかな成長を支える団体のはずです。共働き世帯が増える中、その役割や分担について改革が始まっているものの、更なるスピードアップが望まれています」 とはいえ、負のイメージがつきまとう「PTA役員」も、実際になってみると思いのほかメリットを感じられる局面もある。PTAの活動を通して、我が子が通う学校に横のつながりができる点だ。「PTA役員」を経験して良かったと答えた保護者の理由の最多も<保護者間のネットワークが広がった(43.2%)>だった。 保護者同士のみならず、校長や教頭を含めた教員、古くから地元で商売をしているOBなど、「PTAネットワーク」を通じて広がる人脈は、親として心強いものであることは間違いないだろう。
今回は、PTA役員になって「メリットを享受」している母親がいるとのことで、東京都在住の波多野真美さん(仮名・37歳)に取材する機会を得られた。 波多野さんのお話によると、新年度がはじまり、PTA役員を選出するための総会が小学校体育館で開催されたそうだ。波多野さんの学校は、ほぼ共働き世帯のため、役員のなり手が見つからず、総会が荒れるのは毎年恒例のことだという。 ところが、昨年度は「私で良ければ…」と手をあげる母親が現れたのだ。 彼女は、転入生の母親で「早く親子で学校に馴染めればいいかなと思いまして…」と動機を述べ始め、他の保護者からは「おおっ!」「素晴らしい!」などと賞賛の嵐だったという。ただし、彼女からは、「私、PTA役員やりますよ。その代わりに…」と「ある驚愕の条件」が提示されたのである。それは、彼女が就いている仕事の営業だった。 PTAネットワークを通じての営業は許されるものなのか。そこまでしないと役員が決まることはないのか。 なり手の少ないPTA役員事情。特に共働き世帯の父兄からは、PTA活動に時間を取られることが懸念されている。
【関連記事】「PTAネットワーク」を使って露骨に商売を始める「PTA役員」が爆誕! その豪胆すぎる立ち回りと成り上がり術にもはや感服!
では、PTA役員に立候補した女性からの条件にモヤモヤする父兄と感服する父兄の両側面をリポートします。 ※ 取材対象者のプライバシー保護のため一部、改変しております。ご了承ください。 取材・文/中島はるき PHOTO:iStock